身延道/みのぶみち
身延道のルート
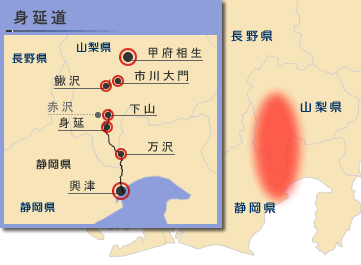
身延道は駿河の国で東海道から別れ、身延を通って甲斐の国甲府の相生で甲州街道と接続する約80kmの道のり。
<東海道>(興津[おきつ])-(宍原)-(万沢[まんざわ])-(南部)-(身延)-(下山)-(飯富)-(切石)-(西島)-《ルート分岐 ①(鰍沢[かじかざわ])-(青柳)-(浅原) ②(市川大門)-(布施)》-(山之神)-(河東中島)-(西条)-(甲府相生)<甲州街道>
注)東海道の由比、岩淵から万沢へ北上する道もある。
身延道の別名
河内[かわうち]道(富士川流域の河内領内を南北に通過するので)、甲州往還、駿州往還、甲駿往還、駿甲脇往還、身延街道
身延道の歴史
身延山参詣の信仰の道
日蓮宗総本山・久遠寺[くおんじ]と開祖・日蓮(1222~82)の廟所に詣でる日蓮宗(法華宗)信者の信仰の道である。特に10月13日(日蓮の入滅日)の大会式前後は、遠近各地から老若男女の信者が殺到する。
なお日蓮は鎌倉から弟子と共に南部を経由して波木井(身延)入りしている。1274年以来、8年余身延山から一歩も出ることはなかったが、その後病気療養のため下山した。それは不帰の旅路となった。
武田信玄の戦いの道
戦国時代には武田一族の穴山氏の支配地を通る軍事道路だった。
よく整備され重要な役割を果たした。また街道周辺には、武田信玄の隠し湯として知られる下部[しもべ]温泉があり多くの湯治客が往来した。JR身延線・下部温泉駅からバス7分。
駿河[するが]と甲斐を最短コースで結ぶ古道
三大急流の一つ・富士川(他に最上川、球磨川)の西岸沿いに街道は発達したが、徳川家康の命で京都の豪商・角倉了以[すみのくらりょうい]が開削(1607)して以来、その舟運に頼る旅人も多かった。「下げ米、上げ塩」と呼ばれた。
下り荷は幕府への年貢米で、鰍沢~岩淵までの72kmを半日で下った。逆に上がり荷は塩などの海産物で4~5日を要した。
身延道歩き旅アドバイス
道筋が不明の箇所が多いので要注意。
所々に街道説明板は建つものの、その前後の道筋を示す指示標がない。無理せずに興味があるところだけピックアップするのもよい。逆に言えば探険欲をそそられる街道だ。
身延道歩きコースプラン
今回の歩き旅
身延山と修験の霊山・七面山[しちめんざん](1982m)を結ぶ参道は、本来の身延道ではないが、その途中にある赤沢宿は重伝建(重要伝統的建造物群保存地区)にセレクト(1993)されているので、赤沢までの魅力ある山道をドッキングすることによって歩き旅の充実を図った。
なお、この道は江戸中期に整備された参道で七面参道、身延往還、身延山追分道などと呼ばれている。
身延道歩きのコース
| コース | プラン | |
|---|---|---|
| 1 | 興津~西行峠 | (興津)-(但沢)-(宍原)-(万沢) 余裕があれば西行峠 |
| 2 | JR身延駅~下山 | (JR身延駅)-(三門)-(東谷参道日朝通り)-(下山) |
| 3 | 身延山~赤沢宿 | 身延山~身延往還を通り赤沢宿へ |
| 4 | 鰍沢~市川大門 | (鰍沢)-(青柳)-(市川大門) JR身延線にて帰途に着く(甲府or富士) |
Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.
