西近江街道 街道歩き旅
〔大津~敦賀編〕
大津~敦賀の位置

いにしえの街道
国道161号線(右)との分岐点に建つ道標

小野妹子公園
大津市唐臼山古墳。遣唐使小野妹子の墓と伝わる

苗鹿(のうか)の常夜灯
西近江街道沿いでは、最大級の常夜灯。1847年建。雄琴温泉の手前

本堅田の榎
右に道標(1836年)が建ち、「白髭大明神 右〇〇」とある。

日吉大社の山王祭
ここ坂本は延暦寺の門前町。
かつて日吉大社は山王信仰と日吉参詣で賑わった。

武者姿の稚児。実にあどけない。

「花渡り」
山王祭の中では最も華やかな行事である。

警護の若者(左右)を従えて参道を進む

日吉大社の参道を上る「花渡り」の行列

色とりどりの造花で飾った献花

以上撮影は、2003年4月13日

テレホンカード
「堅田の落雁」は、安藤広重による浮世絵版画。
浮見堂(右下)を背景に飛ぶ雁の群れ。
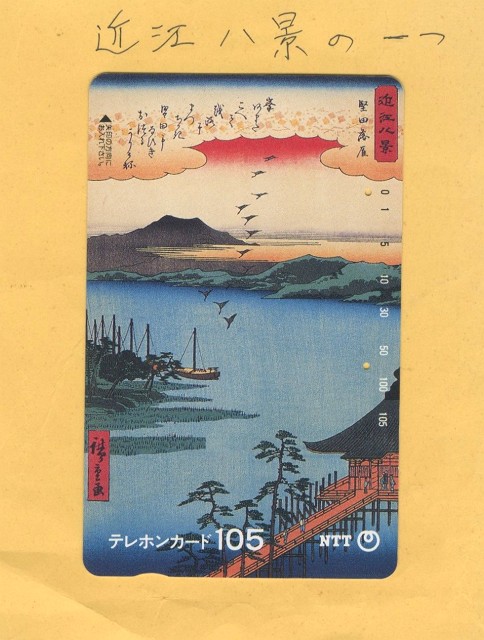
陽明園
日本に陽明学を広めた中江藤樹(1608~48)は、高島市生まれの儒学者。 「近江聖人」と尊称された。

陽明園
道の駅「藤樹の里」の東側にある中国式庭園。
(中央にある陽明亭は、2018年に老朽化により解体)

佐々木神社の竹馬祭
この竹馬祭は400年近い歴史があるという。以前は戸主となる長男だけの行事だったが、今は村の男児すべてが参加する。

流鏑馬
馬(本物の馬ではなく、1mぐらいの竹で作られた馬)にまたがって、走りながら矢を放つ。
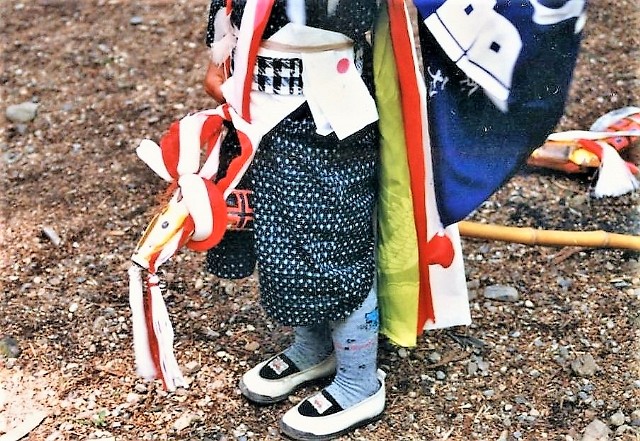
拝殿の前で「弓の手」。次いで「扇の手」が馬場である。

佐々木神社 竹馬祭
新旭町熊野本今市 佐々木神社1988年撮影

新旭町安井川にやってきた
今から大荒比古神社の七川祭が始まる。行列が当番の家を出発したところ。

唐丁(からな)(中央)が持つ竹
竹の上には酒が入っている。適宜自分で飲んだり、祭りの見物人に勧める。
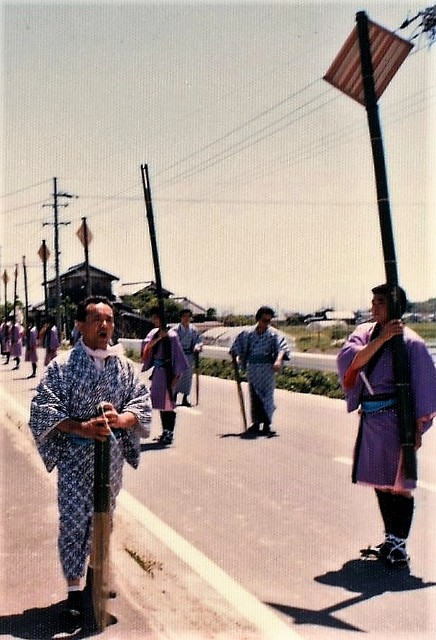
流鏑馬の青年(中央)

的練(まとねり)
奴姿で的を持ち練り歩く的練(まとねり)

樽振(たるふり)
酒樽をかつぎ、ユーモラスに振り歩く樽振(たるふり)。
人気者で笑いを誘う

鉦たたきの子ども(中央)
当番の家に男児がいないと、借りてくるらしい。

長い行列
田園の中を、かなり長い行列が進む。

的練りの奴が神社の境内に入ってきた。
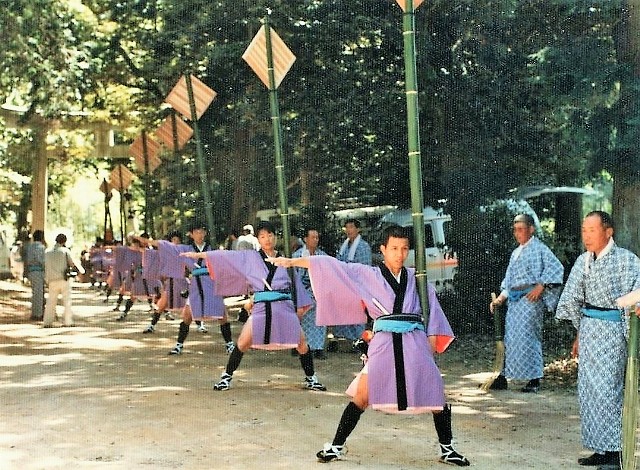
「ええ祭りや」と地元の人
地元の人は、本当にこの日が楽しみのようだ。神社内の桟敷で御馳走を親戚や家族と食べ、酒を飲み、馬駆けを見物していた。

馬駆け
騎馬武者の馬が、約300mの馬場を駆け抜ける。

傘鉾の入場
鉾の数は、旧八ヵ村の数。色は白と赤。
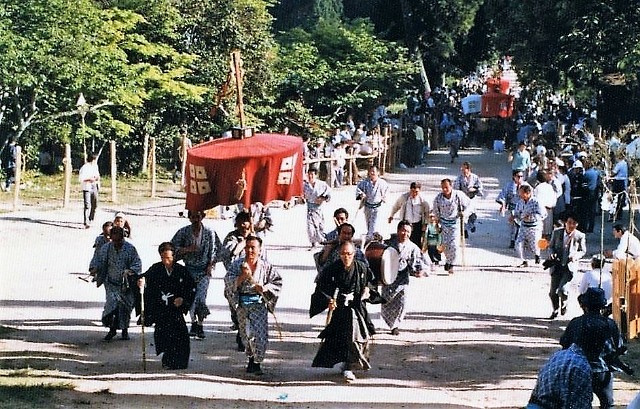
湖西地方最大の祭り

大荒比古神社の七川祭
1986年5月10日撮影

新旭風車村の花ショウブ園
大荒比古神社から東へ約4kmのところにある。

駄口一里塚(敦賀市)
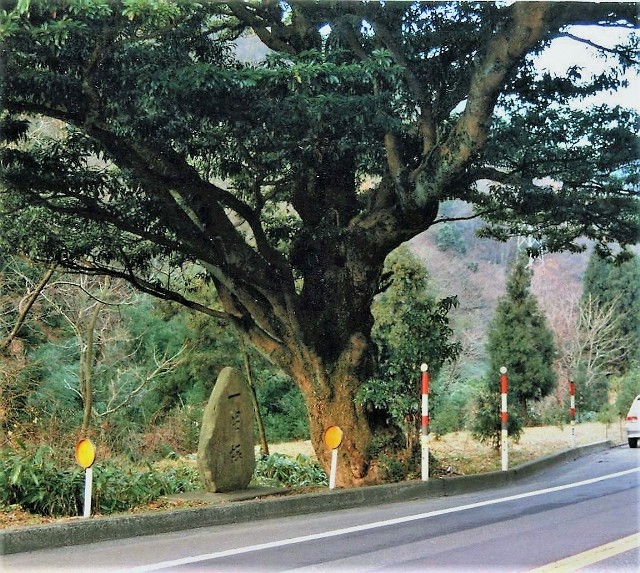
疋田の道標(1873年)
「右 西京、かい津(海津)、志ほつ(塩津)」「左 東京 きの本道」

西近江街道歩きコース
| コース | 見どころ、ハイライトなど | |
|---|---|---|
| 西近江街道 | 西近江街道トップページへ | |
| 1 | 大津~敦賀 | 山王祭,竹馬祭,七川祭 |
Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.
